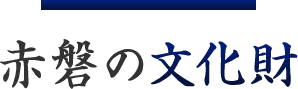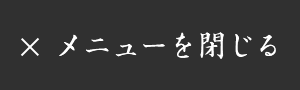備前周匝茶臼山城址
| ふりがな | びぜんすさいちゃうすやまじょうあと |
|---|---|
| 所在地 | 赤磐市周匝 |
| 時代 | 室町~安土桃山時代 |
| 調査年 | 1985年 |
| 調査主体 | 吉井町教育委員会 |
| 参考文献 | 「備前周匝茶臼山城址発掘調査報告書」 1990年 岡山県吉井町教育委員会 |
概要
城は標高約170メートルの茶臼山の尾根上に築かれました。発掘された主郭は尾根の先端部に設けられ、南北55メートル、東西38メートルの広さをもった不整円形を呈します。
縄張(なわばり)を見ると、尾根上に郭面が2面設けられ、尾根鞍部に堀切、南斜面に竪堀を備えており、北西側には大仙山城を築いています。城全体は南側の防御意識が強く、これは宇喜多直家の北侵に対抗したものと思われます。
調査では、柱穴・溝・土壙や地下式の居住施設と思われる大形竪穴遺構が見つかりました。遺物は中国産の陶磁器や備前焼・常滑焼などの焼物、砥石・臼・硯の石製品、鏃・刀子・小札(こざね)の鉄製品、鍔(つば)・銭貨・こうがいの銅製品のほか、瓦や羽口(はぐち)などが出土しました。築・廃城の時期は16世紀後半と考えられます。現在は「城山公園」として整備されています。
主郭:山城や砦などの中心区画。
縄張:山城や砦の設計・計画。
堀切:尾根を仕切るように造られた堀。
竪堀:斜面に対して縦方向に造られた堀。
小札:甲冑などを作るために用いられた、小孔が空いている長方形状の鉄板。
こうがい:髪を整えるため用いられた、箸に似た細長い道具。
羽口:炉の下側などに設けられた、ふいごなどの送風装置から風を送るための送風口。

主郭の全景

大形竪穴遺構の近景
更新日:2018年03月01日