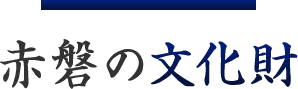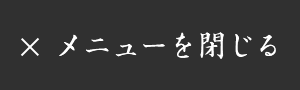着銅遺跡・山の間遺跡
| ふりがな | ちゃくどういせき・やまのまいせき |
|---|---|
| 所在地 | 赤磐市長尾 |
| 時代 | 弥生~古墳時代 |
| 調査年 | 2012・2015年 |
| 調査主体 | 赤磐市教育委員会 |
| 参考文献 |
「赤磐市文化財調査報告 7」 2014年 赤磐市教育委員会 「赤磐市文化財調査報告 11」 2017年 赤磐市教育委員会 |
概要
遺跡は砂川西岸の平野に面した北にのびる尾根の東斜面に立地し、砂川をはさんで東岸には斎富遺跡があります。着銅遺跡と山の間遺跡は同一斜面にあり、一体の集落と考えられます。
弥生土器が多く出土しているため、弥生時代から遺跡が形成されたと思われますが、主には古墳時代中期後半から後期にかけての集落です。見つかったのは竪穴住居19軒、段状遺構19基などで、住居の斜面上方には雨水などが流れ込まないよう溝をめぐらせていました。また、住居の多くにカマドを造り付けていました。
造り付けカマド:古墳時代に朝鮮半島から伝わった住居内の炊事施設で、鍋や甑をかけて煮炊きや蒸す調理を行いました。

尾根の斜面に築かれた着銅遺跡

山の間遺跡で見つかった竪穴住居
斜面上方には溝、住居内にはカマドを設置
更新日:2022年05月06日