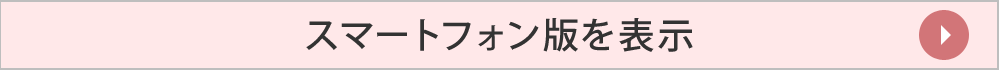田園に響き渡る笑い声〜落語女優、元祖住みます芸人に会いに行く

どうも~、ようこそのお運びで。
わたくし、山本真由美でございます。
えー、相変わらずのところでのお付き合いを願いますが、、、
O橋「なんですかその口調?」
山本「私、落語を少々嗜んでおりまして、落語をする女優だからってんで『落語女優』と名付けて活動をしてるんでございまして」
O橋「つまり落語で言うところの『まくら』の語りってことですか」
そもそも男性が多い落語の世界。
落語女優にはあらゆる可能性が詰まってるわけなんですが、その話しはまた次の機会を待つとして、、、
あーた、すっかりおなじみの赤磐市に、フゥテンの落語家がいらっしゃるっていうじゃーありませんか!
しかも、なーんにもない田んぼのど真ん中で、毎月のように落語の寄席が行われてるって?
そりゃもう正気の沙汰じゃないかもしんない。
てやんでぃ!あちきをそこへ連れてっておくんなまし!
O橋「分かったからその口調やめてください」

そんなことを聞きつけ、やってきました赤磐市は赤坂地区。
清々しいほどに山と田んぼに囲まれた、とても気持ちのよいこんな場所に、、、

ホントにありました、「お笑い赤坂亭」。

迎えてくれたのは華やかなピンクのお着物が映える、落語家の雷門喜助師匠。
一端の落語に触れる者として、落語の、そして人生の大先輩に、是非お話を伺いたい!

山本「いったいなぜここで、落語をやられているんですか??」

喜助「たまたま乗り込んだ新幹線がね、岡山止まりだったんですよ」
そんな嘘みたいな本当の話。
終点が別の場所ならこの「赤坂亭」も無く、今の喜助師匠も存在しないわけで、流れに身を任せる様はみごとなフゥテンっぷり。
喜助「若い頃にNHKで新人賞を穫ったんですよ、落語で。そのままの勢いでラジオ番組なんかを持ったりしましてね。東京でやってたんですけど、忙しくなるにつれて自分のやりたい落語の方ができなくなった。 若かったというのもありますが、その変化のスピードについていけなくなって、全部やめて新幹線に飛び乗ったんです。」

終点の岡山で下車して、岡山人生がスタート。
そこでもまた不思議なもので、落語を通じて喜助師匠の運命は動いてゆく。
喜助「岡山で暮らし始めて、はじめはふらふらしていたんですが、落語のおかげでいろんな良いご縁がありまして。とある旅館で寄席のお仕事をいただいたり、その寄席の噂が広まって、岡山のテレビ局で番組を持つことになったり」

山本「こちらにいらっしゃってからも、やっぱりご活躍で!」
喜助「おかげさまでね。だけどそればかりやってるとまた東京と一緒になりますからね、同時に岡山で寄席を定期的にやるようになりました」
自分の本来の仕事をやらなければと、岡山市で寄席を続けていた喜助師匠。
喜助「ある日、赤坂(現赤磐市赤坂地区)に出前寄席にきたら、当時の町長につかまったんですよ。『うちの町に来てくれ』と言われて。『いい条件でもあれば』と冗談半分でいったら、『家を提供する』って言うんですよ」
山本「町長さん本気ですね」
喜助「それが行ってみるとぼろぼろの家でしてね(笑)。いろいろ中を改装してもらってやっと今の家になるわけですが、住んでるだけでは町おこしにならないということで、寄席をしてお客さんを呼べる場所として『赤坂亭』を作ることになりました」
そんな赤坂亭も、2016年の5月で20周年を迎えたとのこと。

喜助「ここを作ったのが50歳の時で、岡山に住みだして30年。私こそ元祖の『住みます芸人』ですよ(笑)。おかげさんで、近所から野菜果物頂いて、周りの方には助けてもらってます」
街の方々から慕われ、自然と人が集まる。「赤坂亭」は街の社交場にもなってるんですね。
喜助「ここには、東西からたくさんの落語家が来るんです」
山本「上方落語と江戸落語を同時に堪能できるのは贅沢ですね」
喜助「日本中探してもなかなかそんな寄席はないですよ、しかも入場料はワンコイン。普通じゃ考えられません」
山本「本当に!私が俳優仲間と寄席をするときも、場所の費用やら何やらでどうしても割高になってしまいます」
喜助「『公営で一番大きいのは国立演芸場、2番目は、ここです』というネタをね、よくやったりします」

『赤坂亭』での活動を中心に、落語や講演会でお呼びのかかる全国津々浦々を、忙しく飛び回っているんだとか。
喜助「私は創作落語もよくやるんです。何年か前に赤磐市が合併した時なんかも、市内を歩いて見て回って、ネタをね、考えました。観光の助けになればと」
今も創作し続ける、進化をやまない喜助師匠の姿勢がまぶしすぎます。
山本「亡くなった父も落語家なんですが、私もひょんなことから落語をやらせてもらう機会がありまして、、」
喜助「そうでしたか。じゃあせっかくだから、襲名披露も兼ねて一席やってみますか。ご近所さんも呼んで」
山本「はい!勉強させてください!」

急いで着替えます(一人だとちょっと大変)。
山本「お待たせしました!」
喜助「じゃ、はじめましょ」

と、ふかふかの座布団の上に鎮座する喜助師匠、、、
ちょっと、これだと、、、
わたくしが真打ちになってしまうじゃありませんか?!
O橋「いい度胸してますね」

岡山といえばの『桃太郎』のお話をとっかかりに、わかりやすい言葉で、大人も子供も楽しめるお話が次から次へ。

その技術もさることながら、自然体というか、街の方々との信頼関係の成せる技なのでしょうか。いつのまにか、肩肘張らない心地よい空気が出来上がっていて。
場の雰囲気に併せて、いろんな冗談を交えたお話から、なるほど〜っと感心するお話まで、喜助師匠のお噺は飽きることなくみんなを引き込んでいきます。



しかし、楽しい時間も終わり…。


喜助「では、次どうぞ。」
山本「は、はいっ」
ひぇ〜!
笑ってばかりですっかり気を抜きまくってました〜!
ものすごく良い感じに温めていただいたとはいえ、、、
やっぱりやりにくいです〜!!!(笑)

師匠にも見守られながら…、私も高座にあがらせていただきます。

ネタは最近覚えたてだった “悋気の独楽”を やることに
※『悋気の独楽(りんきのこま)』
女性の嫉妬(悋気)をテーマにした上方落語の演目。

小さなお客さんには分かりにくいことこの上ないネタですが(汗)。

わたくしがんばりました!

喜助師匠のするどい眼差し。

にやり。

お粗末様でした〜〜!
喜助「いや〜、思ってたより本格的でびっくりしましたよ。今度また赤坂亭でやったら?」
山本「ほんとですか?ほんとに来ますよ(笑)」
//////////

即席寄席の後、 喜助師匠が見せてくださったのは『落語家名鑑』。

そこには、父(桂米八)の名前も。
上方落語家の娘として生まれ、落語は身近な存在だったけれど、私が落語に興味を持ったのは大人になってから。
それまでは、あまりに身近すぎたのと、芸の厳しさを真横で見ていたので、安易には触れられない領域でした(今もそうだけど)。
私が生まれた年から、落語家でありながらも「曲独楽」(独楽を使った曲芸。江戸時代から親しまれる大衆演芸)という道を選んだ父。
紹介文の初めに、私が今日やった演目『悋気の独楽』の文字があった偶然には驚きました。

「自分に無いもの」ではなく「有るもの」に目を向けだせた頃。
女優をしながらも、東京で落語をやるきっかけを頂いたりして、 さすがに黙って、、、とはいかず、 初めて父に『教えてください』と教わった演目は『動物園』でした。
この日。
初めて、桂文喬師匠に頂いていた名前 『桂喬香』 を名乗って落語をしました。
落語×女優=落語女優!
私だからやれることがあるんじゃないかと思っていて、こうして落語をきっかけに出逢えた喜助師匠のお話を伺って、その思いを強くすることが出来ました。

喜助「毎年小学校で寄席をするんですが、子供達がだんだん小話を作れるようになってくるからね。最後にちょっとお題を出すんですよ。そしたら、はじめは簡単なだじゃれだけど、だんだんストーリーを作りた出すから、褒めるんです。褒められると嬉しくて励みになるから、また作る。そしたらおもしろいじゃないですか」
山本「 落語の英才教育ですね!羨ましいなぁ 」

とめどなく飛び出す喜助師匠のお話はみんな興味深くて。色濃い人生が血となり肉となり、飽きること無くすべてがお噺に昇華していく。それこそが芸の道なんだなあ。

こぢんまりとしたこの街に、街の方々はもちろん日本中から落語家を集めてしまう、とてつもなく大きな人がいらっしゃいました。
喜助「私はここにいるんで、気楽にいつでもきてもらって」
山本「はいっ!」
《喜助師匠に会える!落語の聖地・赤坂亭》
落語家、雷門喜助師匠による月1回の定例寄席(毎月第4土曜日)や、 地区の催しなどでも出前寄席を開演しています。詳しくはコチラ。
アクセス
〒701-2203 赤磐市惣分256山陽自動車道/山陽IC車で約30分
お問合せ
電話番号/086-957-4824(赤磐市赤坂支所産業建設課)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総合政策部 政策推進課 地域創生班
〒709-0898 岡山県赤磐市下市344
電話:086-955-1220 ファックス:086-955-1261開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁